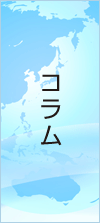コラム
お茶を濁さない関わり
「若者のお茶離れ」などと言われ、家庭で急須が使われることが少なくなったようですが、日常の中で茶を飲んで育ってきた者としては、その時々の気分に合わせて茶葉を選び、お茶をいただくと心が落ち着きます。とろっとした甘いお茶も良いけれど、ふだん好んで飲んでいるのは在来種という昔ながらの日本茶です。素朴な味で、身体に自然に染みていく感覚が心地良いので、いつからか定番になりました。
茶と人との歴史は長く、お茶に関することわざや慣用句もたくさんある中で、“お茶を濁す”という言葉があります。その場を取り繕ってやり過ごすことを指すもので、どうやら素人が抹茶を点てて濁ってしまったときに、いい感じにごまかそうとしたことから生まれたようです。こう聞くとネガティブな印象を受けますが、私たちの生活はいつも期待通りに事が運ぶわけではありませんし、あれもこれもやり遂げようと気を張り続けていては行き詰ってしまうでしょうから、その場に応じて「ここは見なかったことにしよう」とか「とりあえずこのぐらいにしておこう」などと適度に“お茶を濁す”ことは大切なのかもしれません。
一方で、対人援助の場面では、支援者はお茶を濁さずに力を注ぐことが求められます。しかし、問題解決の途中で出くわす多くの困難を前に、支援者自身が不安や戸惑いを感じることもあり、真摯に向き合ったつもりでも、「苦し紛れにごまかしてしまったのではないか」とか「十分に役に立てなかったかもしれない」と反省することもしばしばです。特に、加害者臨床の領域では、面接対象者のニーズをくみ取るのが難しい場合も少なくないため、“お茶を濁さない関わり”を頭の隅に置いて支援にあたるように心掛けています。
日本茶は、茶葉や湯の量、湯の温度や抽出時間などで(同じ茶葉とは思えないぐらい)味が大きく変わります。淹れる人の“関わり方”で味が変わるという難しさや面白さを楽しみながら日々の心理臨床に臨んでいます。(鍋島宏之)